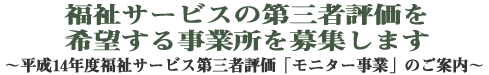
過去の更新記事
平成14年11月11日~平成15年1月10日
平成15年1月10日
介護保険サービスの対価に係る医療費控除について
国税庁の通達を記載致しました。
いよいよ、平成14年分所得の確定申告の時期が近づきましたが、ご存じの方も、ご存じ無い方も、一通り目を通しましょう。サービス事業者の方は、ご利用者やそのご家族からの問い合わせに備えましょう。
介護保険関連情報のページに記載されています。同ページの居宅介護サービス利用料の医療費控除について当施設としての見解もご覧頂ければ幸いです。
平成15年1月9日
第18回社会保障審議会介護給付費分科会の開催について
厚生労働省に掲載されている内容です。
厚 生 労 働 省
平成15年1月9日
第18回社会保障審議会介護給付費分科会を次により開催いたしますので、お知らせいたします。
日時
平成15年1月20日(月)
14時~16時30分
場所
霞ヶ関東京會舘 ゴールドスタールーム
東京都千代田区霞ヶ関3-2-5 霞ヶ関ビル35階
議題
1.介護報酬見直し案について
2.その他
傍聴者
若干名
募集要領
・傍聴の申し込みは、分科会の開催の都度に実施します。
・今回の傍聴申し込み締め切りは1月15日(水)です。
・葉書又はファクシミリ(03-3595-4010)にて事務局までお申し込みください。
・(お名前、所属、電話番号、FAX番号等連絡先をお知らせください。電話でのお申し込みはご遠慮ください。)
・希望者が多数の場合は、抽選を行い傍聴できない場合もありますので、ご了承下さい。抽選の結果、傍聴できる方に対しては後日、FAXで傍聴券を送付いたしますので、傍聴券を受付に提示し傍聴してください。(傍聴できない方には特段通知等いたしません。)
・分科会は原則公開とします。
・カメラ等の撮影については、頭取りとします。
・記者及び傍聴者については、次の「傍聴される方への注意事項」を厳守のうえ、会議を傍聴することができるものとします。
事務局:老健局老人保健課
総務係・企画法令係
TEL 03-5253-1111(内3938・3948)
--------------------------------------------------------------------------------
傍聴される方への注意事項
会議の傍聴にあたり、次の留意事項を遵守して下さい。
これらをお守りいただけない場合は、退場していただくことがあります。
1.事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。
2.携帯電話、ポケットベル等は、電源を必ず切って傍聴してください。
3.写真撮影やビデオカメラ、テープレコーダー等の使用はご遠慮下さい。
4.静粛を旨とし、意見聴取の妨害になるような行為は慎んで下さい。
5.意見聴取における言論に対し賛否を表明し、又は拍手をすることはできません。
6.傍聴中、新聞又は書籍の類を閲覧することはご遠慮下さい。
7.傍聴中、飲食及び喫煙はご遠慮下さい。
8.傍聴中の入退室はやむを得ない場合を除き慎んで下さい。
9.銃器その他の危険なものを持っている方、酒気を帯びている方、その他秩序を乱す恐れがあると認められる方の傍聴はお断りいたします。
10.その他、分科会長及び事務局職員の指示に従うようお願いします。
平成15年1月3日
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。
明けましておめでとうございます。当施設は、本日が年明けの仕事始めとなり、デイサービス事業を開始致しました。
昨年に引き続き、よりよい介護サービスの充実を目指しますので、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
※余談ですが、w32/klez.h@MM(クレズ)というコンピューターウイルスが出回っているみたいです。このウイルスは種別 : インターネットワーム、危険度 : 高 、主な発病 : 大量メール送信/アプリケーションの動作の妨害となっているようです。
ききょの里にも「ws.scr」というファイル名で送られて来ました。ウイルス駆除ソフト等により対策を取りましょう。
平成14年12月25日
第5回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について
会員専用サイトの、wamnetに掲載されています。会員以外の方はご覧になれません。
1.試験期日 平成14年10月27日(日)
2.合格者数等
| 受験者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) | |
| 第5回(平成14年度) | 96,207人 | 29,505人 | 30.7% |
3.これまでの試験の合格者数等
受験者数 合格者数 合格率
| 受験者数(A) | 合格者数(B) | 合格率 (B/A) | |
| 第1回(平成10年度) | 207,080人 | 91,269人 | 44.1% |
| 第2回(平成11年度) | 165,117人 | 68,081人 | 41.2% |
| 第3回(平成12年度) | 128,153人 | 43,854人 | 34.2% |
| 第4回(平成13年度) | 92,735人 | 32,560人 | 35.1% |
| (再掲) 第5回(平成14年度) |
96,207人 | 29,505人 | 30.7% |
| 第1回~第5回合計 | 689,292人 | 265,269人 | - |
以上がwamnetに掲載されている内容の一部です、詳しくはPDFファイルでご覧下さい。
平成14年12月19日
平成15年度税制改正の概要(厚生労働省関係)
会員専用サイトの、wamnetに掲載されています。会員以外の方はご覧になれません。
厚 生 労 働 省
平成14年12月
1.医療関係
(1)医療機器関係
① 医療安全に資する医療機器等についての税制優遇措置の創設 〔所得税、法人税〕
・ 看護業務省力化機器の範囲を見直し、医療安全に資する医療機器等について、取得価額の20%の特別償却を認める。
② メディカル・フロンティアに資する救急用医療機器についての特別償却制度の適用期限の延長(2年間) 〔所得税、法人税〕
③ 医療用機器に係る特別償却制度の適用期限の延長(2年間) 〔所得税、法人税〕
(2)医療提供関係
① 社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置の存続 〔事業税〕
② 医療法人に係る事業税(社会保険診療報酬以外分)の軽減措置の存続 〔事業税〕
③ 社会保険診療報酬の所得計算の特例の存続 〔所得税、法人税〕
④ 特定医療法人に係る要件の緩和 〔法人税〕
・ 特定医療法人について、差額ベットに関し、全病床数に占める割合の上限を30%(現行20%)に引き上げ、平均料金の上限規制(現行5,000円)を撤廃する等の承認要件の緩和を、承認要件遵守のための所要の措置を講じた上で行う。
(3)医療施設関係
① 改正医療法の構造設備基準に適合した病院への建て替えに係る特別償却制度の適用期限の延長及び有床診療所への拡充 〔所得税、法人税〕
・ 建替え病院用建物の特別償却の対象資産に一定の有床診療所の療養病床を加えたうえ、その適用期限を2年間延長する。
② 療養病床に係る割増償却制度の適用期限の延長(2年間) 〔所得税、法人税〕
③ 国立病院・療養所の再編成に係る移譲等を受けた場合における登録免許税の軽減措置 〔登録免許税〕
・ 公的医療機関の開設者等が国立病院等に係る土地等取得した場合の所有権移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、所要の経過措置を講じたうえ、廃止する。
(4)その他
① 造血幹細胞移植・臓器移植のあっせんに係る患者負担の医療費控除の適用 〔所得税、住民税〕
・ 造血幹細胞移植・臓器移植を受けるために必要なあっせん業務に係る患者負担について、あっせんに係る費用の位置付けを明確化した上で、15年所得より医療費控除を適用する。
② 試験研究費の総額に係る税額控除制度の創設 〔所得税、法人税〕
・ 増加試験研究費の税額控除制度との選択制で、試験研究費総額の8~10%の控除率(試験研究費の売上金額に対する割合に応じ控除率を設定。なお、3年間の時限措置として控除率10~12%)による税額控除を認める。
③ 産学官連携の共同研究・委託研究に係る税額控除制度の創設 〔所得税、法人税〕
・ 大学、公的研究機関等との共同試験研究及びこれらに対する委託試験研究について、これらの試験研究に係る試験研究費の額の12%相当額の税額控除を認める(3年間の時限措置として控除率15%)。
④ 中小企業技術基盤強化税制の拡充 〔所得税、法人税〕
・ 中小企業技術基盤強化税制について、試験研究費の総額の12%相当額の税額控除を認める(3年間の時限措置として控除率15%)。
※ ②~④の税額控除については、当期の法人税額全体の20%相当額を限度とし、その超過額については、次年度に限り、繰越控除を認める。
⑤ 開発研究用設備の特別償却制度の創設 〔所得税、法人税〕
・ 一定の開発研究用設備の取得等をして、これを国内にある開発研究の用に供した場合には、その取得価額の50%相当額の特別償却を認める。
⑥ 介護納付金課税額の課税限度額の引上げ 〔国民健康保険税〕
・ 現行7万円→8万円
2.子育て支援関係
① 小児慢性疾患にかかっている児童の家族支援を行う公益法人を特定公益増進法人への指定要件の追加 〔所得税、法人税〕
・ 小児慢性疾患にかかっている児童が療養を受けるために当該児童及びその家族が宿泊する施設の設置運営を行う公益法人を特定公益増進法人として指定できる措置を講じる。
3.高齢社会関係
① 厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金、勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約に係る積立金に対する特別法人税の凍結の延長(2年間) 〔法人税、住民税〕
② 確定拠出年金の拠出限度額の取扱い 〔所得税、法人税、住民税、事業税〕
・ 確定拠出年金の拠出限度額の引上げについては、「長期検討とする」とされた。
4.介護関係
① 介護老人保健施設の割増償却制度の適用期限の延長(2年間) 〔法人税〕
② 老人性痴呆疾患療養病棟の割増償却制度の適用期限の延長(2年間) 〔法人税〕
③ 介護サービス事業を行うN P O法人(特定非営利活動法人)に関する税制上の支援の充実 〔法人税、事業税等〕
・ 認定N P O法人の認定要件の緩和。(いわゆるパブリックサポートテストに関し、総収入金額のうちに寄附金総額の占める割合を3分の1以上から5分の1以上とする(3年間の時限措置)、特定非営利活動が複数の市区町村で行われていること等の活動等の範囲に関する要件を削除する等)
・ 認定N P O法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額については、その収益事業に係る寄附金の額とみなすとともに、寄附金の損金算入限度額を所得の金額の20%とする。
④ 民間介護保険加入者に係る所得控除の創設 〔所得税、住民税〕
・ 生損保控除については、医療、介護など高齢化社会における社会保障政策を踏まえた新たな商品開発の進展との関係、地震災害に対する国民的な備えが重要であるとの見地、制度創設の目的が達成されているとの指摘等を踏まえ、早急に制度のあり方の抜本的な見直しを行う。
⑤ 介護報酬の見直しに伴う介護費用に係る所得控除の取扱い 〔所得税、住民税〕
・ 平成15年4月からの介護報酬の見直しに伴い、介護費用のかかる所得控除について所要の整理を行う。
5.就業環境・勤労者福祉関係
① 住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除措置の適用要件の緩和 〔所得税〕
・ 住宅ローン減税の適用を受けていた者が転勤等やむを得ない事由により一度転出した後、再居住した場合について、一定要件の下、控除の残余期間について、住宅ローン減税を再適用する。
② 住宅用家屋に係る登録免許税の軽減措置の適用期限の延長(2年間) 〔登録免許税〕
6.障害者関係
① 身体障害者居宅生活支援事業等の用に供する資産に係る非課税措置の継続 〔固定資産税〕
② 介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業の第二種社会福祉事業への追加に伴う税制上の所要の措置 〔固定資産税等〕
③ 障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限の延長(2年間) 〔所得税、法人税〕
④ 心身障害者を多数雇用する事業所に係る不動産取得税及び固定資産税の軽減措置の適用期限の延長(2年間) 〔固定資産税、不動産取得税〕
7.生活衛生関係
① 生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長(2年間) 〔法人税〕
② 生活衛生同業組合等の留保所得の特別控除制度の適用期限の延長(2年間) 〔法人税〕
③ 生活衛生同業組合等の貸倒引当金の特例措置の適用期限の延長(2年間) 〔法人税〕
④ 中小企業者等の事業基盤強化設備に係る特別償却制度等の適用期限の延長(2年間) 〔所得税、法人税〕
8.その他
① 特殊法人等改革に伴う税制上の所要の措置 〔法人税、事業税等〕
・ 特殊法人等整理合理化計画に基づく特殊法人等改革に伴い、税制上の所要の措置を請じる。
<対象法人>
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、労働福祉事業団、全国社会保険労務士会連合会、勤労者退職金共済機構、日本障害者雇用促進協会、雇用・能力開発機構、社会福祉・医療事業団、心身障害者福祉協会、社会保険診療報酬支払基金、厚生年金基金連合会、石炭鉱業年金基金、日本労働研究機構
② 死亡牛化製処理場に係る税制上の特例措置の創設 〔固定資産税、事業所税〕
・ 牛海綿状脳症対策実施のため整備される死亡牛の化製処理の用に供する設備等に対する特例措置を新設。 (固定資産税)
・ 家屋及び償却資産について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1(2年間) (事業所税)
・ 施設に対する資産割に係る非課税措置
③ PFI事業の推進を図るための税制上の所要の措置 〔不動産取得税、固定資産税、都市計画税〕
・ 民間の資金や人材、技術等を効率的に用い、国による公共事業に代わって公的インフラの整備・有効活用を促進し、かつ景気対策にも資するP
FI事業に関し、その形態、進展等を踏まえ、税制上の必要な措置を引き続き検討する。
④ 産業活力再生特別措置法の抜本強化に伴う税制上の所要の措置 〔所得税、法人税、登録免許税、不動産取得税〕
⑤ 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(WAC法)に基づき整備される特定民間施設に係る特例措置の適用期限の延長(2年間) 〔特別土地保有税等〕
⑥ 消費生活協同組合等の留保所得の特別控除制度の適用期限の延長(2年間) 〔法人税〕
⑦ 自賠責共済の運用益等にかかわる責任準備金の非課税制度の創設 〔法人税等〕
・ 自賠責保険の運用益積立金等の非課税措置については、交通事故被害者対策等への配慮が必要であることを踏まえ、自賠責保険の公的な性格を反映した運用、事業支出等についてのルールの整備を前線に、早急に結論を得るよう、引き続き検討を進める。
⑧ 外形標準課税の導入についての雇用に配慮した検討 〔法人事業税〕
・ 外形標準課税については、平成15年度に資本金1億円超の法人を対象として、外形標準の割合を4分の1とする外形標準課税制度を創設し、平成16年度から適用する。
なお、制度創設に当たっては、雇用の安定と資本の充実について十分な配慮措置を講ずるものとする。
平成14年12月18日
「医療保険制度の体系の在り方」「診療報酬体系の見直し」について
(厚生労働省試案)の意見募集
厚生労働省に掲載されている内容です。
この試案は、先般の健保法改正法の附則第2条第2項において、平成14年度中に「基本方針」を策定することとされている
(1)保険者の統合再編を含む医療保険制度の体系の在り方
(2)新しい高齢者医療制度の創設
(3)診療報酬の体系の見直し
について、厚生労働省において、広く各方面の議論に供するための「たたき台」としてとりまとめたものです。
幅広く御意見を募集いたします。
今後、この試案をたたき台として、関係各方面からいただいた御意見を踏まえて今年度末に「基本方針」を取りまとめます。
記
1 提出先 厚生労働省保険局総務課
2 提出方法
(1)郵送 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
(2)FAX 03-3595-2258
(3)電子メール ttkdai@mhlw.go.jp
3 電話照会先
総括関係・・・・・・・保険局総務課 内線3218、3219
被用者保険関係・・・・保険局保険課 内線3247
国民健康保険関係・・・保険局国民健康保険課 内線3258
診療報酬体系関係・・・保険局医療課 内線3288
4 募集期間 平成14年12月18日(水)~平成15年1月31日(金)
「医療保険制度の体系の在り方」「診療報酬体系の見直し」について
(厚生労働省試案)
目次
○概要
○本文
○財政試算
平成14年12月13日
特定扶養控除は存続、配偶者控除は原則廃止
読売新聞の掲載内容です。
自民、公明、保守の与党3党は12日夜、都内のホテルで幹事長・政調会長会談を行い、2003年度税制改正の焦点となった所得控除の廃止・縮小に関し、高校・大学生の子供を持つ親を対象とした特定扶養控除(25万円)の廃止を見送ることで合意した。
専業主婦がいる世帯の税負担を追加的に軽減する配偶者特別控除(最高38万円)は2004年1月以降、原則廃止する。これにより、与党は税制改正の大枠を固め、13日に税制改正大綱をまとめる。差し引きの先行減税額は1兆7000―8000億円になる見通しだ。
与党は11日、両控除の廃止でいったん合意したが、公明党は12日、「二つの控除を同時に廃止すれば、中堅サラリーマンの負担は一気に増える」として、特定扶養控除の廃止に反対する方針に転換。自民、保守両党もこれを受け入れた。
公明党が所得控除廃止の見返りに求めた児童手当の拡充について、与党3党は2004年度から支給対象を、現行の未就学児童から、小学3年生まで広げることで大筋合意した。児童手当の拡充を含めた少子化対策の追加額は、年間2500億円となる。
一方、与党は12日の与党税制協議会で、たばこの税率を来年7月から1本当たり1円引き上げ、酒類は同5月から、発泡酒1缶(350ミリ・リットル)を10円、ワインも1瓶(720ミリ・リットル)10円引き上げることなどで正式合意した。
益税解消に向けた消費税改革では、簡易課税制度を利用できる事業者の基準を現行の「年間売上高2億円以下」から「同5000万円以下」にすることなども決まった。
(12月13日01:50)
たばこを吸う人とお酒を飲む人にとってはつらいですね。
平成14年12月12日
社会保障審議会介護給付費分科会(第17回)議事次第が
wamnetで公開されています
会員専用サイトの、wamnetに掲載されています。会員以外の方はご覧になれません。
議題は、「介護報酬の見直しについての考え方」です。
Ⅰ 基本的な考え方
介護保険制度施行後初めてとなる今回の介護報酬の見直しにおいては、限られた財源を有効に活用するため、効率化・適正化と並行して、制度創設の理念と今後の介護のあるべき姿の実現に向けて、今回は、必要なものに重点化した見直しを行うことが大切である。
このため、在宅重視と自立支援の観点から、要介護状態になることや要介護度の上昇を予防し、要介護度の軽減を図るとともに、要介護状態になっても、できる限り自立した在宅生活を継続することができるよう支援する。また、いったん施設に入所した場合でも、在宅生活に近い形で生活し、将来的には、できる限り在宅に復帰できるよう支援する。
また、ここの利用者のニーズに対応した、きめの細かく満足度の高いサービスが提供されるよう、サービスの質の向上に重点を置いた見直しを行う。
さらに、痴呆ケアの確率と質の確保を図る。
なお、施設と在宅の関係、施設ごとの特性や経営主体による諸規制等にも配慮することが必要である。
Ⅱ 具体的な方向
1.居宅介護支援(ケアマネジメント)
居宅介護支援(ケアマネジメント)の業務の実態等を踏まえ、利用者の要介護度に応じた包括単位を廃止し、要介護度に関わらない一律の評価とする。
また、居宅介護支援の質の向上を図る観点から、一定の種類数以上のサービスを組み合わせた場合を評価するとともに、利用者の居宅の訪問など一定の要件を満たさない場合の評価を見直す。
2.在宅サービス
(1)訪問介護
訪問介護の適正なアセスメントを図る観点から、身体介護と家事援助が混在した複合型を廃止する。また、「家事援助」から「生活援助」に名称を改めるとともに、短時間のサービス提供や生活援助について、自立支援、在宅生活支援の観点から適切に評価する。
さらに、訪問介護の質の向上の観点から、3級訪問介護員によるサービス提供の場合の減算の算定範囲を拡大する。
いわゆる介護タクシーについては、適切なアセスメントの下に、算定対象を限定し、適正化を図るべきである。
(2)通所サービス
要介護者の在宅生活を支援するとともに、利用者の利便性の向上や家族介護者の負担の軽減を図るため、6~8時間の利用時間を超えてサービスを提供する場合を適切に評価し、延長加算を新設する。
(3)訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション
円滑な在宅生活への移行、在宅での日常生活における自立支援を図る観点から、訪問リハビリテーションを評価するとともに、通所リハビリテーションについて、個別的なリハビリテーション計画に基づくサービスを評価する。
(4)居宅療養管理指導
きめ細かく個別的な指導管理の充実を図り、利用者の在宅生活における質の長期的な維持・向上を目的として、月当たり算定回数や単位数の再編を行う。
(5)痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)において、痴呆性高齢者が安定的に自立した生活を営むことができるよう、夜間のケアを含めたサービス内容についての入所者ごとのアセスメント等を行うとともに、夜間介護体制の整備されたグループホームについて、夜間ケア加算を新設する。
3.施設サービス
(1)特別養護老人ホーム
画一的な集団処遇ではなく、在宅での暮らしに近い日常の生活を通じたケアを行う観点から、入所者の自立的生活を保障する個室と、少人数の家庭的な雰囲気の中で生活できるスペースを備えた小規模生活対応型特別養護老人ホーム(仮称)で行われるユニットケアを評価する。これに伴い、居住費について自己負担を導入し、低所得者対策も講じた上で、在宅との費用負担の均衡を図る。
また、特別養護老人ホームにおいて要介護度の高い者について報酬上も配慮する。
(2)老人保健施設
入所者の介護度の改善と在宅復帰を進める観点から、老人保健施設において、日常生活動作等の維持・向上を重点とした個別的なリハビリテーション計画に基づくサービスを評価するとともに、老人保健施設が行う訪問リハビリテーションを評価する。
(3)介護療養型医療施設
介護と医療の役割分担、他の介護保険施設との役割分担を図る観点から、長期にわたる療養の必要性が高く、要介護度の高い者の入院を評価する。また、個別的なリハビリテーション計画に基づくサービスを評価する。
経過措置に従い、療養病床を有する病院の看護職員6:1/介護職員 3:1の人員配置の評価を廃止する。
さらに、介護保険適用病床と医療保険適用病床の機能分化を図る一方で、介護保険と医療保険の制度の狭間で患者の受け入れ先がなくなることを防ぐため、一定の医療処置を要する者を対象に、重度療養管理を新設する。
なお、介護報酬設定における人員配置の評価の在り方については引き続き検討することとする。
(4)施設入所者の在宅復帰の促進
施設入所(入院)者の在宅復帰を指向したサービスを評価し、在宅復帰を促進するため、退所(退院)前の施設と居宅介護支援事業所の連携を積極的に評価する観点から、退所(退院)時指導加算を再編し、退所(退院)前の連携について必要な加算を新設する。
以上が議事次第の内容の一部です。詳しくは、wamnetをご覧下さい。
平成14年12月5日
セクシュアルハラスメント防止・対応マニュアルを公開しました
既に施行されている男女雇用機会均等法第21条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)に基づいてのことですが、安心して働きやすい職場づくりを目指し、被害者の保護だけではなく、加害者又はご利用者も保護するために設置致しました。
セクシュアルハラスメント防止・対応マニュアル
平成14年12月1日
第16回 社会保障審議会介護給付費分科会の内容が
厚生労働省より公開されています
以下の項目は、厚生労働省のページからリンクしてあります。
| 1. | 議事次第 | ||||||||||
| 2. | 資料1
|
||||||||||
| 3. | 資料2
|
||||||||||
| 4. | 資料3
|
||||||||||
| 5. | 新井委員提出資料 | ||||||||||
| 6. | 木村委員提出資料 | ||||||||||
| 7. | 中村委員提出資料 | ||||||||||
| 8. | 痴呆性高齢者グループホーム評価調査員研修テキスト(省略) | ||||||||||
| 9. | 第14回介護給付費分科会議事録 | ||||||||||
| 10. | 第15回介護給付費分科会議事録 |
照会先 老健局 老人保健課 企画法令係 TEL 03(5253)1111(内3948 3949)
平成14年11月11日
全社協より福祉サービスの第三者評価「モニター事業」を募集しています
//www.keieikyo.gr.jp/keieikyo-hyoka/
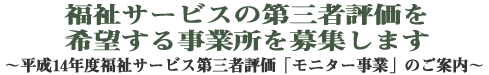
![]()
介護保険制度の施行、社会福祉基礎構造改革の進展、さらに平成15年度からは障害福祉サービスが支援費制度へと移行するにともない、福祉サービスの質に対する関心が高まっています。
このような状況のもと、全国社会福祉協議会は厚生労働省の国庫補助事業として、福祉施設等における第三者評価の受審促進に向けた啓発を図るとともに、評価情報の活用や、より効果的な評価手法の開発等、望ましい第三者評価システムの構築に資するため「福祉サービス第三者評価「モニター事業」」を実施します。
![]()
本事業は,第三者評価を希望する福祉施設等に「モニター事業所」としてご応募いただき、その中から50事業所程度を選定、実際に第三者評価を受けていただくものです。
本事業における第三者評価機関は、全国社会福祉協議会が実施した「平成14年度評価調査者養成研修会」に参加した団体のうち、実際に第三者評価を行うことを希望した9つの団体が登録されています。登録にあたっては、本事業を公正かつ円滑に実施することを目的として設置している「福祉サービス第三者評価モニター事業運営委員会」による選考を行っています。
「モニター事業所」には、
第三者評価受審に向けた準備と実際に第三者評価を受けていただきます
評価結果は、施設名等を含めて広く公開させていただきます
第三者評価を受けた感想や課題等についてアンケート調査等をさせていただきます。
なお、本事業において第三者評価を受けていただく際の料金は不要です。
![]()
「モニター事業所」を募集します。
応募締切り:11月29日(金)
モニター事業において受審を希望する1つの第三者評価機関を選んでいた
だき、所定の方法でご応募ください。
「モニター事業所」を選定します。
ご応募いただいた中から50事業所程度を選定させていただきます。
選定は、「福祉サービス第三者評価モニター事業運営委員会」が応募の状
況等を勘案して行います。
「モニター事業所」となっていただく施設等には、12月中旬を目途に事業
の詳細をご連絡いたします。
第三者評価を受けていただきます。
ご応募の際にお選びいただいた評価機関による第三者評価を受けていただき
ます。(平成14年12月末~平成15年2月上旬を目途としています。)
第三者評価の進め方や日程等は各評価機関とモニター事業所の間で個別にお
決めいただきます。
評価結果等のとりまとめと公開
評価結果は、WAM NET等において広く公開いたします。
第三者評価を受けた感想や課題等についてモニター事業所から広く意見をお
寄せいただきます。
![]()
第三者評価機関一覧をご参照の上、希望する機関をお選びください。その際、対象地域ならびに対象事業が、貴施設等に該当しているか十分ご確認ください。
ご応募は、本ホームページからのみの受付とさせていただきます
以上のページは社会福祉法人全国社会福祉協議会において//www.keieikyo.gr.jp/keieikyo-hyoka/ に記載されている内容です。
| |
mail to:kikyou@kikyou.or.jp
社会福祉法人 桔梗会
〒378-0002群馬県沼田市横塚町957-2
℡0278-23-8831(代) FAX0278-23-8832
All Rights Reserved, Copyright(C)kikyou. 2002